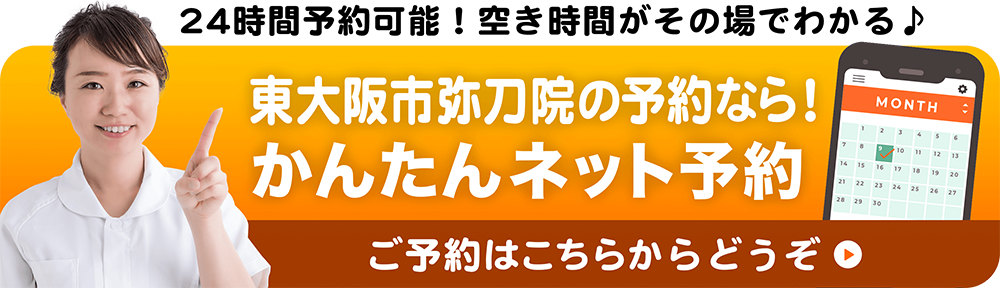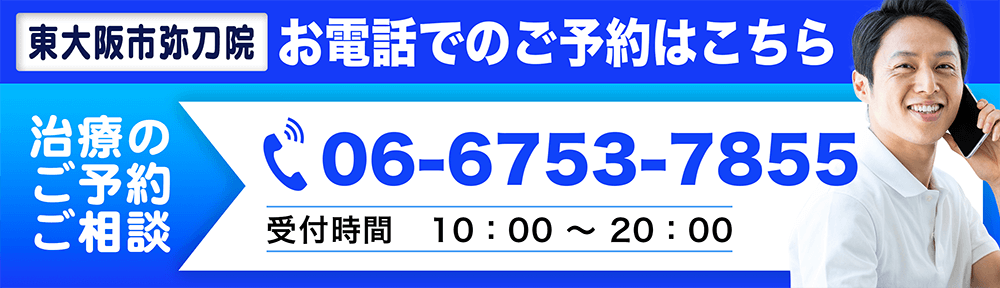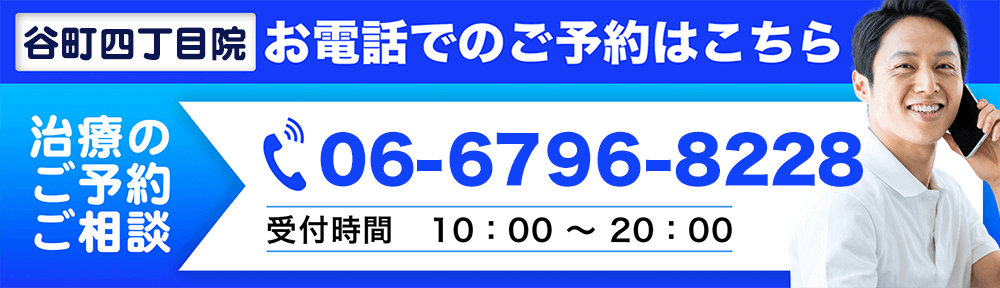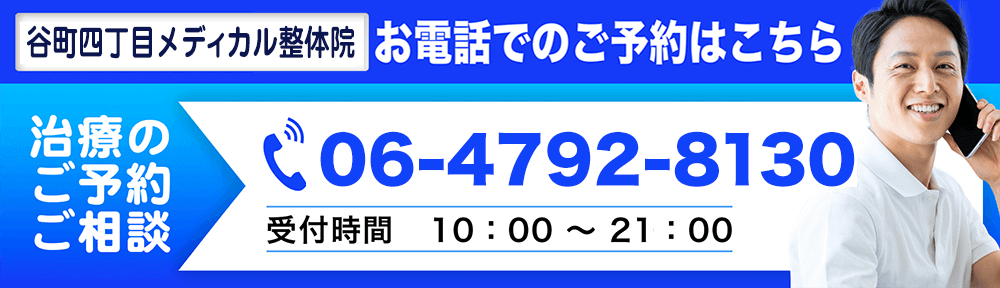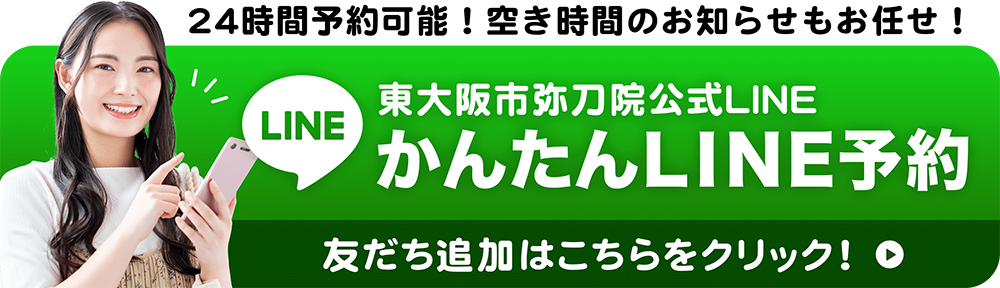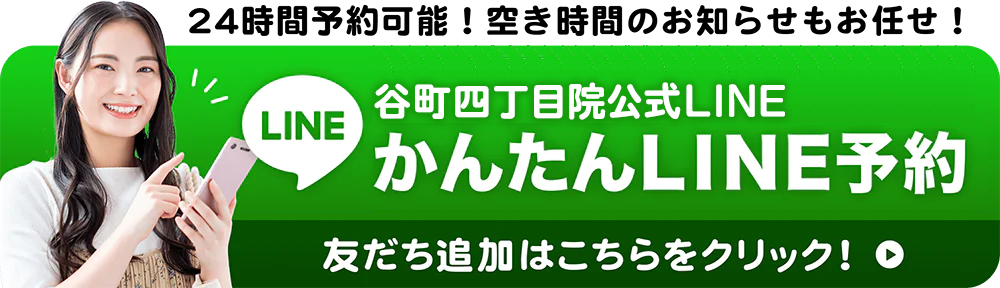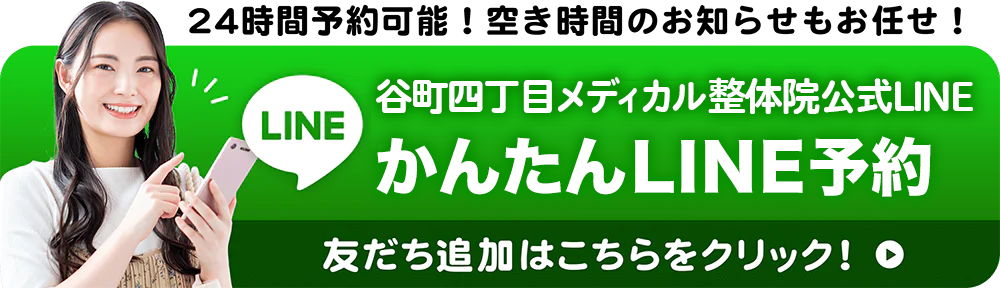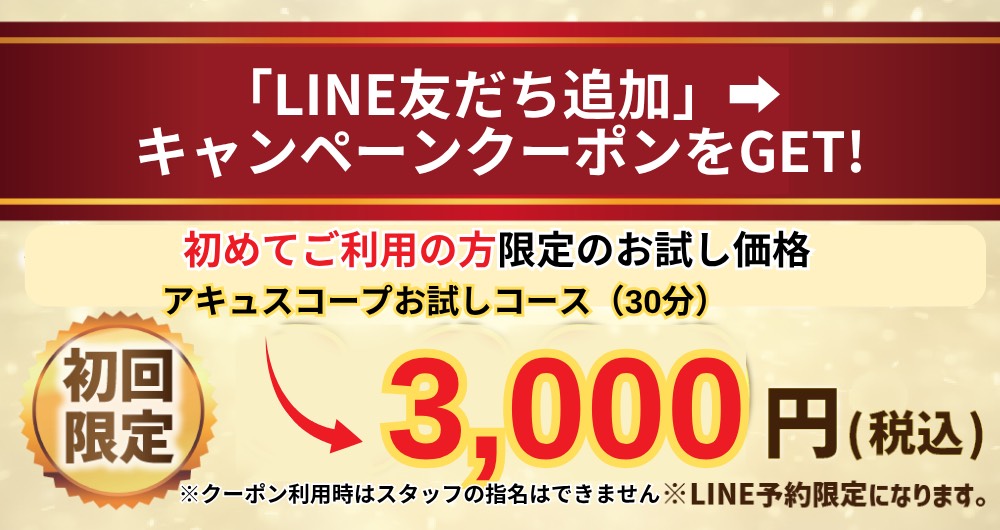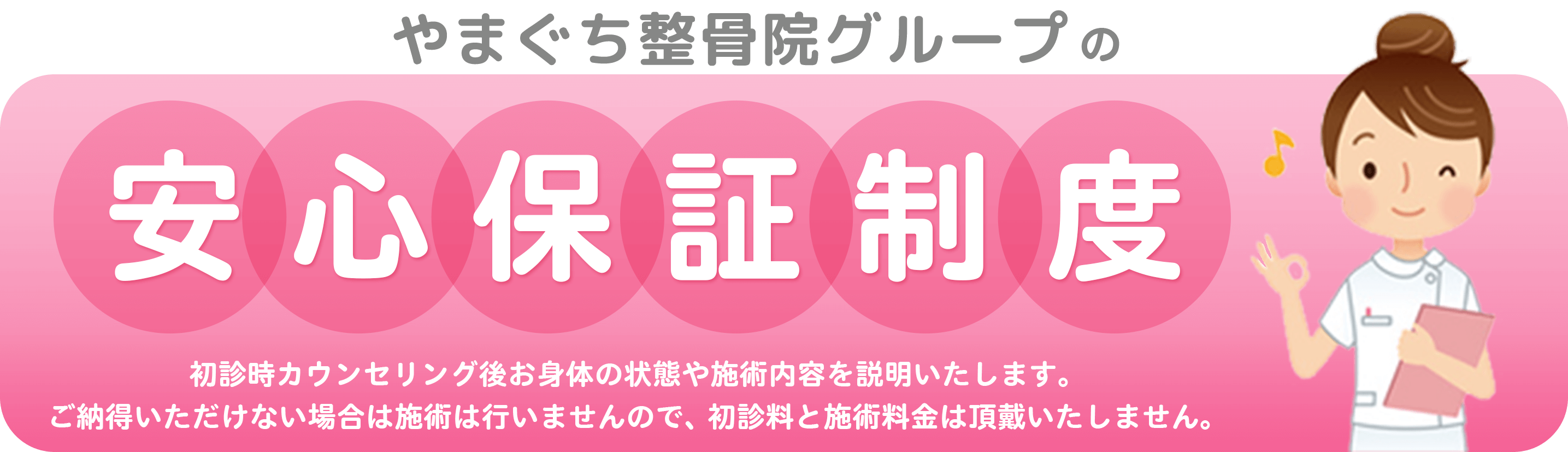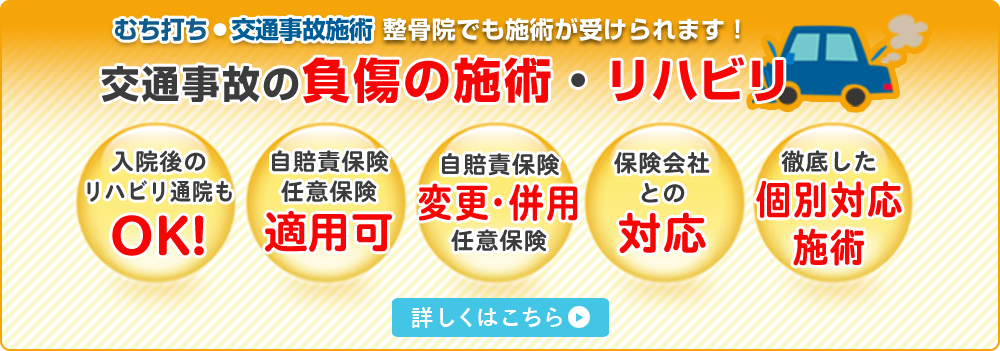歌手の背中の役割
歌と背中の関係について ~響きと支えの源としての背面の役割~
歌を歌う時、私たちは一般的に声帯や呼吸、あるいは表情や口の開き方といった、比較的「前側」の身体部分に意識をむけがちです。
しかし、実は「背中」が歌唱において極めて重要な役割を果たしています。
背中は単なる身体の裏側ではなく、呼吸、姿勢、声の響き、精神状態にまで密接に関係する”声の支え”の中心です。
背中と呼吸機能の関係
歌の根本となるのは呼吸です。
そして呼吸は、肺そのものというよりも「肺が広がる空間」すなわち胸郭に支えられています。
胸郭は背骨(胸椎)を中心としうて背中側にも大きく広がっており、そこを支えているのが脊柱起立筋や広背筋、肩甲骨周囲筋などです。
特に深い息(腹式呼吸)を吸い込む時、横隔膜は下降し、肋骨が外側・後方へと広がります。
この時、背中が柔軟である事が重要です。
背中が硬くなっていると、肋骨の動きが制限され、十分に空気を取り込む事ができなくなります。
また吸気だけでなく、呼気においても背中の働き、息をコントロールして吐き出す「支え」の役割をになっています。
背中と声の響きの関係
歌声の「響き」は共鳴によって生まれる。
声帯で作られた音は、喉、口腔、鼻腔、胸腔などに響きながら増幅される。
この時、響きが前方だけでなく、「後方」すなわち背中の方にも広がっていく事が、豊かで深みのある声を生むためには欠かせない。
特にクラシック声楽や声の演技をようするミュージカルなどでは、「後頭部や背中に声を当てる」「肩甲骨の奥に響かせる」といった
イメージが使われることもあります。
これは物理的に音が背中に響いているというよりも、背中全体を「共鳴空間」として活かす事で声が立体的に、そして楽に響くようになるという発声法上の感覚を意味します。
姿勢と背中の連動
歌うときの姿勢は、ただ「まっすぐ立つ」ことではない。
背骨の自然なS字カーブを保ちつつ、肩や首に無駄な力を入れずに、全身
リラックスしていながらも芯が通ってる状態が理想的です。
この姿勢を保つ上で重要なのが背中の筋肉です。
脊柱起立筋が過緊張していたり、逆に弱すぎて姿勢が崩れていると、呼吸も浅くなり喉にも余計なちからが入ってしまいます。
結果として、声が硬くなる、響きが狭くなる、音程が不安定になるといった問題が生じやすく
なります。背中の柔軟性と適度な筋力は、安定した発声の基礎なのです。
背中と心のつながり
背中はしばしば感情や精神状態を反映する部位でもあります。
「緊張すると肩が上がる」「不安があると背中が丸くなる」といった経験は誰にでもあるでしょう。
実際、背中には副交感神経の通り道である迷走神経の一部が走行しており、ここが硬直しているとリラックスした呼吸や発声が妨げられます。
歌をうたうことは、感情表現そのものであり、そのためには心と身体の両方が自由である必要があります。
背中の緊張を解くことは単に肉体的な効率を高めるだけだけでなく、感情の流れを滑らかにし、より深い表現を可能にします。
音楽整体ならやまぐち整骨院グループへ

やまぐちスポーツ整体院:谷町四丁目駅4番出口徒歩1分(谷町四丁目院同じビルの4階)
全院、微弱電流機器「アキュスコープ」「マイオパルス」ハイトーン機器「ハイチャージ」を完備。
微弱電流機器は我々が触診では確認できない体内の電気信号を機器自体が読み取り、正しい電気信号に書き換えることで身体本来の治癒力を引き出すことが出来ます。
ハイトーン機器は我々が活動するためのエネルギーを生成している「ミトコンドリア」を活性することで、内臓疲労・筋肉疲労・冷えなどを含めた体に起きうるあらゆるストレスに効果が期待できます。
これらの機器を使用することでストレスのたまりにくい身体づくり、持久力が向上し、演奏や歌での表現力豊かなパフォーマンスが可能になります。
更に必要に応じてストレッチ、運動療法、トレーニングなど機能改善の施術も行っております。
日頃のメンテナンスとしてもご利用ください。
症状によって来院回数、期間は異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さいね。